CASE 16 緑翳和邸
(今回は、オーナー金出武雄様が寄せて下さった顛末記をお楽しみください。)
35年間住み慣れたアメリカを離れ日本に自宅を建てようと思い立ち、建築会社をインターネットであたっていると、偶然に「ALL」のホームページに行き当たりました。なるほど、どれも質の高い味わいのある建物だけれど、考えている予算ではチョッと無理かなとおもいつつ、おそるおそる社長の篠田潤氏にメールしたのがそもそもの始まりでした。以来、ほぼ丸2年にわたって約??千通のメールを、アメリカのペンシルバニア州ピッツバーグと日本の古都京都の間で設計と建築の期間を通してやりとりして出来上がったのがこの緑翳和邸です。
敷地は兵庫県丹波篠山の中心である篠山城跡、今もなみなみと水をたくわえるお堀のすぐ西側で、土地を世話してくださった不動産屋さんによると、もと御徒町として必殺仕掛け人中村主水のような下級武士の武家屋敷の並んでいたところとか。篠山市はそういう風情の残った景観を保存すべく、門塀を含む建物の外観に条例によって制限を加えています。日本風の家に住みたいというもともとあった気持ちが、長いアメリカ生活でいっそう強くなったように思える私たち夫婦には、それは制限というより願ったりの環境でした。と同時に、アメリカ生活で慣れた、自然な庭に囲まれ広くてゆったり明るくて住みよい、つまりすべてよしの家にしたいというかなり贅沢な要求がありました。
日曜大工を始めなんでも自分でする癖があるので、建築家気取りで考えに考え、方眼紙に書いたこういう家をお願いしますと依頼したフロアプランは次のようなものでした。前塀にはギッギーと観音開きに開閉する門、それを入ると前庭の向こうの平屋の建物はまず玄関と客用のスペース、次にはダイニングリビングなど共用スペース、一番奥には書斎を含むプライベートスペースという3つの部分を中庭を囲んでC字型に配置、その向こうには裏庭というものです。ここは切り妻とか、屋根の形まで指定していました。
敷地を見にいっていただいて、篠田氏が最初にいわれたのは「この環境にはゆったりとした大屋根の家が似合いますね。」、「こういう奥に長い敷地では真ん中の縦に長い部分に部屋をただ並べると単調になってよくありません。」でした。しばらくして送られてきたプランは、基本形はほぼ同じでしたが真ん中のリビングルームを中庭に張り出し、その分へこんだ反対側に小さな庭をつくる、つまりアルファベットのE(もっと正確にはギリシャ文字のε)の形にする、そして大きな寄せ棟の屋根にするというものでした。こうすると、「どの部屋からも少なくとも二方向に庭が見える。また、屋根がどの方向にも高さを主張しないので景観として威圧感を与えない」とのことです。その他にもシュークロークなどちょっとした部屋の配置に工夫がある。なるほど、ある意味たったそれだけでこんなに違う家になるものか、それがプロの技というものだと感心し、いっぺんに好きになりました。
思い返してみると、随分やりにくい施主ではなかったかとおもいます。大学教授という職業柄、学生がなにか言ってくるとそれはどうしてか、他にやり方はないかなどと徹底的に聞かないと気がすまない癖がついています。「ここはこういう材質とデザインで」とか話があると、「どうしてその材料なのか? その特徴は? こういうデザインはありえないのか?」と次々尋ねて納得しないと決めないものだから、話がなかなか進まない。よく我慢して付き合っていただいたものと思います。特にこだわったのは、すべての窓に障子をつけてほしい、それも開けているときは目だたず、できれば見えないようにしたいということでした。そのために、「この大きなほぼ全面の窓はガレージドアのように障子は天井裏にしまって置き、閉めるときはそれが上から降りてくるように作れないか」などと「特許の取れそうなデザインの提案」して篠田氏を苦笑させたものです。それは没でしたが、窓の位置、戸袋が入る壁、障子の大きさが実に考えられていて希望が実現されています。
この二年間は世界のどこに行ってもいろいろな建物を見るとその景色、造りや装飾などをつぶさに観察するようになりました。ロシアのセイントペテルスブルグの宮廷風装飾、日本の由緒ある旧家を移築した旅館、中東のカタールの超近代建築、ドイツの田舎町の石畳の味など、わたしなりの面白い発見があると篠田氏にメールを送ったものです。そうして今となっては、「この家は誰でもない『私が』設計したのだ」と、来る客ごとに一つ一つの由来を説明して、いっぱしの建築デザイナーになったような自分を発見すると、私は篠田氏の言われる「建築とはそのプロセスを楽しむものである」というのを本当に地で行った人間と言えるのではないかと秘かに思い、出来上がった家にいっそうの愛着を感じる次第です。
PAGE: 1 / 7
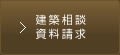
































































.jpg)